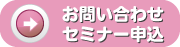女性が正しい知識を身につけ、自分で考え、自分で選択できるようになる、女性のQOL(Quality of Life=生活や人生の質)向上を専門家たちが真剣に考える
第2回「女性のQOLを考える研究会」が8月28日(日)、都内で開催されました。
リオ五輪直後の開催となった今回は、女性アスリートのコンディショニング研究を切り口に現代女性のQOL(生活の質)について徹底議論。
アスリートというとどうしても雲の上の存在のような存在に感じますが、美人化計画の代表・桜井明弘は「女性アスリートが直面している問題は
一般女性の抱えている問題が凝縮されている」といいます。
そこで、
・日本体育大学教授 須永美歌子先生
・順天堂大学女性スポーツ研究センター長 小笠原悦子先生
・広尾レディース院長 宗田聡先生
という女性&アスリートについてのスペシャリスト3名(講演順)にご登壇いただきました。
女性ホルモンのエストロゲンは骨形成にも必要不可欠
大切な試合にぶつかるくらいなら月経がない方がいい」と思うアスリートも少なくありません。
しかし、美人化計画代表で、産婦人科クリニックさくら院長の桜井明弘は、
「出血がないのでいいパフォーマンスが出せるように感じるかもしれないが、卵巣からエストロゲンが出ていないのは問題。
アスリートは主に中学〜大学生など若い人が多く、この時期は骨などが形成される大切な時期。
骨を作るために必要なエストロゲンが分泌されていないと骨密度が低くなる。
将来の骨粗しょう症になる可能性も高く、疲労骨折でアスリート人生が終わってしまうこともある」(桜井)。
そのための対処法としては「低用量ピル(OC)」が有用だといいます。ドーピングで引っかかるかもと敬遠されることもありますが、
「ドーピング検査で陽性反応を示す薬物の主な成分は筋肉増強につながるような男性ホルモン作用のあるもの。
女性ホルモン剤であるピルは引っかからない」のです。

月経周期も味方につけて最高のパフォーマンスを
アスリートたちの多くが、月経がないわけではなく「約6割は正常月経」です。
そのため、この女性ホルモンの波を活かして、いいパフォーマンスを引き出すために研究しているのが、日本体育大学教授の須永美歌子先生。
「月経周期を利用して、今が痩せ期とか、ダイエットしても無駄な時期という俗説がたくさん出回っていますが、科学的根拠がないことが多い」
と、月経周期の血中代謝物質が与える影響を研究しています。
須永先生によると、
「女性ホルモン濃度が高いときの方が脂肪が分解され,痩せやすい」とのこと。
これは、生理前は痩せにくいと言われていた定説とは真逆。
「脂肪を分解しても、それを筋肉でエネルギーとして使わないと燃焼されない。生理前の黄体期に有酸素運運動をすることで脂肪燃焼効果が高まる」(須永先生)。
特に、審美系の競技では体重を気にするアスリートが多いですが、
「女性の平均体重は1ヶ月で2.6kg差が変動する。この体重の増加は脂質ではなく水分によるもの。指導者にもこういう知識が必要」(須永先生)と、
女性ホルモンの周期による影響の周知も重要になってきます。

女性は男性のミニチュア版ではない!
「そもそもスポーツは男性のために作られたもの。女性には月経があり、女性特有の障害や疾患もある。
男性のミニチュア版のように女性を育てることは時代錯誤」と日本に「女性アスリート」という概念を持ち込んだ、女性スポーツ研究センター長の小笠原悦子先生はいいます。
女性アスリートたちが直面する問題は「身体・生理的な課題」のほかに、デュアルキャリア(競技と学業の両立)、
セカンドキャリアなどの「心理・社会的な課題」、そして指導者やコーチになるときの「組織・環境的な課題」など大きく3つあります。
「単発で選手が活躍したり、メダルが取れればいいというのは、もう世界からの尊敬は得られない。
本当に必要なのはドロップアウトすることなく、恋愛、結婚、出産、育児などができること」(小笠原先生)。
こういった概念が世界的に提唱されたのは1994年の「ブライトン宣言」が初めて。しかし日本では2001年とまた15年しか経っていません。
今後はスポーツ組織における女性役員の比率向上や、コーチとしてのセカンドキャリアにも注力していくことになりますが、
「出産、育児をしても競技が続けられるのはもちろんのこと、出産育児をしながらコーチ業を継続させるための環境整備も必要」(小笠原先生)になります。

女性の健康は「心と身体が両輪」
女性の心と体を総合的にサポートする宗田聡先生は「女性の健康は、心身が両輪」だといいます。
特に、摂食障害や体重コントロールは一般の人たちとも共通性の高い問題。摂食障害は単なる食欲や食行動の異常ではなく、
体重への過剰なこだわりや、自己評価など心理的な影響が大きく、心の病気と考えられています。
「女性アスリートに強いられる体型や体重の意識、厳しいトレーニングや重圧は摂食障害の大きなリスク因子。
試合に負けて自信をなくしたり、他人の評価を気にしたり、ストレスを感じることが根底にある。
一般の人の場合も、受験の失敗や失恋、仕事のミスなど、日常生活で似たような状況に置かれる。
また、家族関係、特に母親との関係性も影響しているのが特徴」(宗田先生)だといいます。
摂食障害は将来の妊娠、出産への問題だけでなく、うつ病などメンタルの問題、さらに命に関わる問題として捉えられています。
「きちんと食べてられていないため、健康な人と体の中が全部違っていて点滴をすることで急に体内バランスが変わり危険な状態になることも。
さらに本人は治る気力、生きる気力がない場合も多い」(宗田先生)といいます。
身体だけではなくメンタルも重要、というのは現場で日々実感している事実なのです。

(文/吉田理栄子)