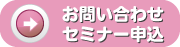体外受精をめぐる最近の報道から 〜生殖医療の逸脱〜
- 2014/8/21
- 医療

この一月も経たないうちに、世間を賑わす体外受精をめぐる問題、報道が複数みられています。
体外受精に代表される、高度生殖医療を行っている私も、とても心を痛め、また止まることを知らない、生殖医療ビジネスの先行きに深い懸念を持っています。
生殖医療がビジネス化することは、早晩予想が付いていたのですが、いよいよその時代が到来したのでしょうか。
最初に飛び込んできたのは、日本国内から。
・「祖父の精子で体外受精、17年で118人誕生」
実母が代理出産するなど、多くの生殖医療モデルを提示してきた長野県の生殖医療施設が、今度は男性不妊のカップルに、ご主人のお父さん、つまり産まれてくる子どものおじいさんに当たる人の精子を使った体外受精を、これまで17年間にわたり、118人の子どもが出生したことを明らかにしました。
体外受精という治療を行うのは、戸籍上の夫婦間に限る、と、我々産婦人科医が所属する日本産科婦人科学会の会告(会員が守らなければならない規約)にあるものの、日本の法律には定めはなく、またおじいさんの精子を使ってはいけない、という規定もありません。
つまり、治療は治療を行う医療機関と、治療される患者さんたちの合意があれば、何ら法的な罰則はないのです。
赤ちゃんが欲しい、切実な願いを持つカップルが、どんな方法を取っても妊娠したい、そんな気持ちは、日々不妊患者さんに接している私にも、十分理解は出来ます。
様々な問題が含まれるこの祖父の精子を使った生殖医療ですが、最も大きな問題は、やがて産まれてくるお子さんの出自を知る権利です。
AID(非配偶者間人工授精)でも同様ですが、精子提供された妊娠の場合、産まれてきた子どもを育ててくれるお父さんが遺伝的な父親ではなく、AIDでは全くの赤の他人、第3者で、今回の治療では、おじいちゃんが遺伝的なお父さんなのです。
比較的血縁を重視する日本の家社会では、お父さんに精子がなければ、おじいさんやおじさんなど、比較的血が濃い関係の精子を使うのは許容される範囲かも知れません。
ただ、それは当事者である不妊カップルはじめ、大人の我々の概念で、産まれてくる当人にとっては、それは選択された出自ではありません。
ましてや長じてその事実を知る時、知る権利と、知った内容に対して多くの問題があるのです。
今回の治療が誤っているのか、正しいのか、それはこの報に接した一人一人が考え、判断するもので、誰もそれを裁くことは出来ません。ただ、我々日本国民の一人として、こう言う治療をどう感じるか、どう考え、許容するのかしないのか、一人でも多くの議論が必要なのです。
是非、今日にでも、ご家族や親しい方と、どう思うか、どう感じたかを話題にしてみて下さい。
次は海外の2つのニュースです。