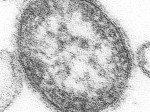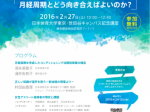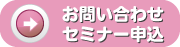第2回「女性のQOLを考える研究会」講師訪問 〜順天堂大学女性スポーツ研究センター長 小笠原悦子先生〜
- 2016/8/20
- Check

第2回「女性のQOLを考える研究会」 二人目の講師は私の母校である順天堂大学より、女性スポーツ研究センター長、小笠原悦子先生にお願いしました。
女性のQOLを考える研究会の詳細はこちら
順天堂大学では2014年10月、女性アスリートを対象とし、無月経や月経痛、月経前症候群(PMS)などの婦人科疾患、疲労骨折などの外傷、そして栄養指導など、総合的な医学サポートを行う「女性アスリート外来」が開設され、多くのアスリートの患者さんの診療と研究がなされています。

その女性アスリート外来の立ち上げから運営まで中心的な役割を担ってらっしゃる小笠原先生。国際的な女性アスリート研究者として大変高名な先生です。
女性アスリート外来診療を代表する北出真理教授のご紹介により、久しぶりに母校、順天堂へ、小笠原先生を訪ねて参りました。
体育研究室のため、てっきり順天堂のさくらキャンパスにお邪魔するものと思っていましたが、女性スポーツ研究センターは本郷キャンパスにもオフィスがあり、先生はそちらでお迎え下さりました。

先生には研究会でアスリートのキャリアについてお話し頂こうと相談。もちろんご快諾頂けたのですが、話題はご講演のみならず、現代の若い女性の運動離れがとても深刻であると。
女子中学生の運動習慣は40%ほど、高校生になると半減するとの調査報告があります。
その減少は、ひとえに運動部を続けなくなることにあるそうです。
反対に全く運動をしない、割合が20%増え、つまり、運動部を辞めてから運動習慣がなくなる女子がとても多いのです。もちろん男子にも共通しますが、もっと遡れば幼少期に屋外で身体を動かして遊ぶ習慣が著しく減っており、長じてからの体力、筋力低下を招いている。
現代女性の健康問題の中でも大きなものに、過度なやせ志向がありますが、成熟期になってから体重を増やそうとしても骨や骨格筋が基本的に形成されていないため、筋力もつきにくい、体重も増えにくい体質になってしまっています。
これはやがて妊娠しにくい身体に繋がるのでないでしょうか。
リオデジャネイロオリンピックでは、女性アスリートの活躍も大変目立ちます。
トップアスリートがさらなる飛躍をするためには、競技人口が増え、切磋琢磨するライバルの存在が不可欠です。
女性の運動離れはやがて、日本の女性アスリートのレベルが下がることにならないか、ということまで懸念される徴候です。

小笠原先生からは、多くの研究成果の中から、単にアスリートの問題に留まらない、国家レベルでの教育問題にまで発展したお話がたくさん伺うことが出来ました。
第2回女性のQOLを考える研究会ご登壇者 須永美歌子先生についてはこちら