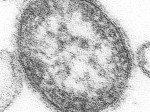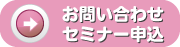先週報道されたニュースです。
体外受精など高度生殖医療(国では特定不妊治療、とよびます)を受けた際に受給できる助成金の支給対象を、これまでの「配偶者に限る」から、「事実婚でも受給可能」とすることを、厚生労働省が検討していることが報じられました。
このニュースに含まれる、一般の方にはあまり知られていない2つの点について解説します。
まず、「不妊治療の助成金制度」について。
一般的に不妊症は病気ではない、という考えに基づき、不妊検査、不妊治療の一部は保険診療対象外、つまり自費診療となります。
排卵日を予測する「タイミング指導」やパートナーの精液を処理して子宮に注入する人工授精がそれにあたります。
これらの一般不妊治療を行っても妊娠しない、または一般不妊治療による治療効果が期待できないカップルが体外受精などの高度生殖医療に進むことになりますが、高度生殖医療は一切の保険診療が認められず、全て自費診療となります。施設によって自費診療価格は異なりますが、数十万の治療となり、いずれにせよお子さんを希望するカップルにとって、治療費は大変重い負担となります。
保険診療は認められないものの、国では高度生殖医療を行った夫婦に対して、自治体を通して自治体と折半で助成金を交付してくれています。
かつてはもっと低額だったのですが、現在では初回30万円まで支給され、治療内容によっては、初回はほとんど自己負担なく治療が可能な場合もあります。
ただし、収入制限があったり、また42歳までに治療を開始しないと受け取ることが出来ません。
支給する自治体、つまりお住まいの自治体によってこれらの諸条件は、一部異なることがあるため、ご自身の自治体のHPなどで確認してください。
さて、次に「事実婚でも」の部分です。
体外受精などの生殖医療には、法律による制限がありませんが、産婦人科医のほとんどが所属する日本産科婦人科学会が規定を設けており、我々産婦人科医はそれに則って治療に当たっています。
2年前の民法改正までは、高度生殖医療を受けるには入籍した夫婦であることが絶対条件でした。そのため産婦人科クリニックさくらでも高度生殖医療を開始するまでに入籍してもらったこともあります。
民法改正により非嫡出子の権利が嫡出子と同じになったことを受け、入籍していない事実婚も同じ対応をすることになったのです。
上に書いた不妊助成金の受給は今でも入籍していることが条件の一つでしたが、今回、厚生労働省が事実婚のカップルも助成金支給対象とすることを検討しています。